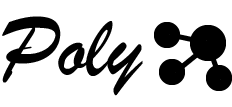介護離職を防止するための要点は2つ「個人の問題と会社の問題」です。
介護離職ゼロを目指して
今、少子高齢化の波が日本に押し寄せ、労働人口(15歳以上で,労働する能力と意思をもつ者の数)がどんどん減少しています。
総務省統計局「人口推計」 によると、2017年の20-64歳の人口はピーク時(1998年度)よりも約900万人も減少しています。企業では今後人手不足が深刻化する可能性が非常に高い状態です。
また、一方で、家族の介護や看護のために離職する「介護離職」は2017年には約9万人となり、2010年代になっておよそ2倍に増えました。(2007年比)今後も増えていく可能性が非常に高いです。
政府は「介護離職ゼロ」に向けた具体策として、
- 介護の受け皿を拡大すること
- 仕事と介護の両立ができること
を示しています。
しかし、なかなか思うようには進んでいないのが現状です。
介護の受け皿を拡大する
65歳以上の要介護(要支援)認定者に対する介護保険3施設( 特養、老健、介護療養型医 療施設)の整備率は16%。 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホームを加えても整備率は32%にとどまり、家族に介護が必要になった時の施設系サービスの不備も指摘されています。
施設に入所できない時には、在宅サービスを使いながら介護することが一般的になっていく可能性が高いのです。
仕事と介護の両立ができる環境が整っている必要があります。
仕事と介護の両立
厚生労働省が立ち上げた 介護離職ゼロポータルサイトによると、大きな2つの課題について言及されています。
- 個人の課題
- 会社(働き場所の環境)の課題
個人の課題

在宅介護で活用できる制度を知る必要があります。
仕事をしながら介護をするとなると、どうしても仕事を休みがちになってしまいます。
介護保険制度などの公的制度を使い、家族以外の外部の方に介護を手伝ってもらえる環境をまず整えることが必要です。
在宅で使える主な公的制度には、介護保険サービスがあります。
介護保険サービスは、所得に応じて1~2割の負担で訪問ヘルパーなどの介護サービスを受けることができます。しかし、無制限にサービスが受けられる訳ではなく、要介護度が認定され、それに応じて限度額が設定され、その範囲内で介護保険サービスを受けることができます。
まずは市町村の窓口で相談し、介護認定を受け、介護度が判定されます。その後、介護保険のサービスを利用していくことになりますが、家族や金銭的なものなど、全体を考慮した上で必要な時に必要なサービスを受ける必要があるので、ケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
ケアマネージャーに相談する時のちょっとしたコツ
今、生活のどんな場面で困っているのか、出来るだけ具体的に相談しましょう。
例えば、「お風呂に入れなくて困っている」場合、
- 原因: なぜ入れないのか?
- 例: 膝が痛くて湯船に座って入浴できない。
- 現状: 湯船に浸からずシャワーで済ましている。
- 具体的に困ってること: シャワーのため、冬に寒くて風呂に入っていられない。
このような相談であれば、デイサービスで入浴するという以外にも、特定福祉用具の入浴台を介護保険制度を利用して導入することで湯船に浸かることができるようになることもあります。
その分、限度額の枠を消費しなくて済むので、他のサービスを利用したり、限度額を有効に使うことができます。
会社(働き場所)の課題

日本の文化と密接に関係している部分でもあります。
長時間労働の是正など「労働時間=価値」という社会全体の考え方を見直していく必要が根底にあるため、すぐには改善は難しいとされていますが、政府主導の働き方改革などにより徐々に意識改革が進んでいます。
介護休職などの所属する会社の制度を利用する
介護離職につながるケースは、正社員が多いというデータがあります。
フルタイムで正社員として働きながら介護をするのは時間的にも体力的にも大変です。
改正育児・介護休業法では、介護休業(93日の休み)や介護休暇(年5日)について規定されています。最近では、介護離職を防止するための介護離職防止制度を設けていることもあるので、会社に相談することも大切です。
「プライベートの話は職場ではしてはいけないもの」という意識がある方も多いため、まずは上司や部下と円滑にコミュニケーションが取れる環境づくりから初めていく必要がありそうです。
まとめ
未来は誰にも分かりません。
しかし、人口統計から導き出される未来予測はほぼ的確に将来やってくるといわれています。
介護離職はこれから社会問題になる可能性が非常に高いです。労働人口が減少していく中、介護離職を防止するためには、大きく、
- 個人の課題
- 会社(働き場所)の課題
の2つを改善していく必要があります。
個人も会社も、社会という大きな受け皿の上で成り立っています。社会的な意識や常識が変わっていけば、少しづつ個人と会社も変化していきます。誰が変える、というのではなく、みんなで社会全体を見直していくことが必要、ということだと思います。